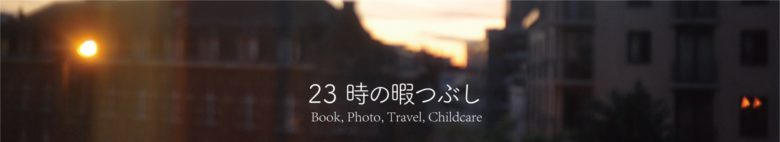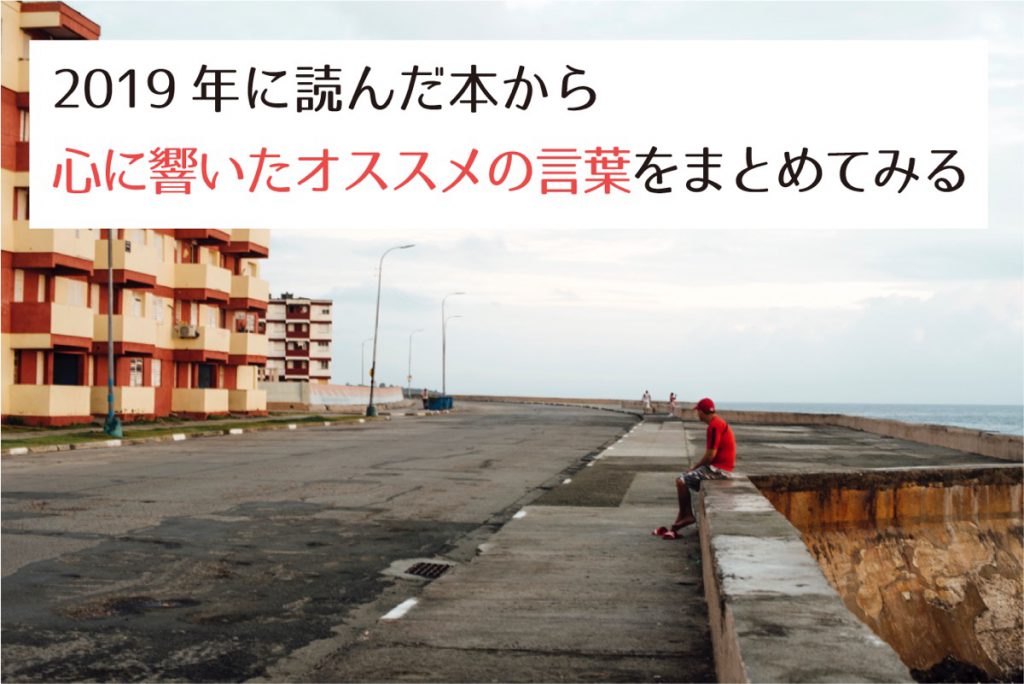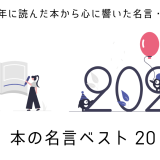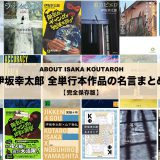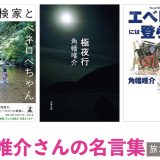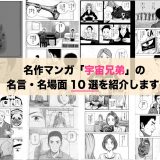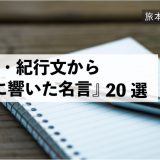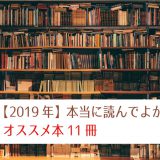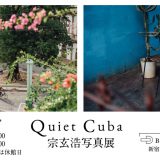「2019年に読んだ本から心に響いた名言・名文」を紹介しています。
2018年から現在まで毎年行っている企画ですので、興味のある方は2018年の名言特集、2020年の名言特集、2021年の名言特集もあるので、本の名言・名文に刺激を受けたい方は、合わせて読んでください!
この記事では、「2019年に読んだ本の中から、心に響いた名言・名文」を紹介しています。
本には言葉のプロたちから生まれた名言・名文がたくさん書かれていて、それらの言葉は僕たちの生活を豊かにしてくれる力があります。
小説、エッセイ、写真集、紀行文など2019年に読んだあらゆるジャンルの本から僕の心に響いた名言集・名文集をまとめました。
2018年から毎年行っている企画ですので、「本の名言集」に興味のある方は読んでみてください!
 【本の名言】2022年上半期に読んだ本の名言集・名文集10選
【本の名言】2022年上半期に読んだ本の名言集・名文集10選目次
- 2019年に読んだ本から選んだ名言集・名文集
- 2019年に読んだ本に書かれた名言集
- 沢木耕太郎『銀河を渡る』の名言
- 『FACT FULNESSファクトフルネス』の名言
- 瀧本哲史『ミライの授業』の名言
- 前田裕二『メモの魔力』の名言
- 木崎伸也『アイムブルー』の名言
- 吉田修一『続 横道世之介』の名言
- 箕輪厚介『死ぬこと以外かすり傷』の名言
- 東松寛文『サラリーマン2.0』の名言
- 荻田泰永『考える脚 北極冒険家が考える、リスクとカネと歩くこと』の名言
- 坪田信貴『世界に一つだけの勉強法』の名言
- 坪田信貴『才能の正体』の名言
- 国分拓『ノモレ』の名言
- 松岡修造『弱さをさらけだす勇気』の名言
- 幡野広志『ぼくたちが選べなかったことを、選びなおすために。』の名言
- 幡野広志『ぼくが子どものころ、ほしかった親になる。』の名言
- 若林正恭『ナナメの夕暮れ』の名言
- 若林正恭『表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬』の名言
- 糸井重里『思えば、孤独は美しい』の名言
- 岸政彦『図書室』の名言
- 中村禎『最も伝わる言葉を選び抜くコピーライターの思考法』の名言
- 本の名言記事で紹介した本はaudibleで聴ける?
- 読書が楽しくなる本の名言を紹介
- 2019年に読んだ本から心に響いた名言 まとめ
2019年に読んだ本から選んだ名言集・名文集
2019年に読んだ65冊から印象的な言葉をまとめてみました
(※後日談 2020年以降もこの企画は継続しています)
本のタイトルや作家名に加えて、読書感想文を書いた本はリンクも載せておきますので興味をもった本があれば読んでみてください。

ここで紹介した名言・名文は「本の面白さ」は関係なく、本に書かれた言葉だけで選びました。
今のあなたを勇気づけてくれるような言葉があるといいですね!
また、2019年に読んだ65冊からオススメの11冊を選んだ記事を書いたので、興味のある方は併せて読んでみてください!
2019年に読んだ本に書かれた名言集
沢木耕太郎『銀河を渡る』の名言

▶『銀河を渡る 全エッセイ』に書かれた名言・名文
そして、その次の瞬間、即席の「イチゴのオハナシ」を作って話しはじめるのだ。早く眠らせるために主人公に果てしなく同じことを繰り返させたり、意味もない言葉遊びで時間をつぶすようなものもあった。そのようにして、いくついい加減なオハナシを作ったろう。
これから出版する児童書は、そのときの「オハナシ」そのものではないが、そのときの記憶がもとになっていることは確かなように思える。
ささやかだけれど、私の人生の中で最も甘やかなものとなっている、遠い過去の記憶が。

なんとも幸せな文章。
この数行を読むだけで幸せな気持ちになれる。
「銀河を渡る」は、2019年に読んだ本の中から第11位に選定し紹介した本です。
また、沢木耕太郎さんは、オススメの旅本やエッセイで紹介しているので、興味のある方は読んでみてください。
『FACT FULNESSファクトフルネス』の名言

▶FACTFULNESS(ハンス・ロスリング)に書かれた名言・名文
「世界では戦争、暴力、事前災害、人災、腐敗が絶えず、どんどん物騒になっている。金持ちはより一層金持ちになり、貧乏人はより一層貧乏になり、貧困は増え続ける一方だ。何もしなければ天然資源ももうすぐ尽きてしまう」
少なくとも西洋諸国においてはそれがメディアでよく聞く話しだし、人々に染み付いた考え方なのではないか。わたしはこれを「ドラマチックすぎる世界の見方」と呼んでいる。精神衛生上よくないし、そもそも正しくない。
時を重ねるごとに少しずつ、世界は良くなっている。何もかもが毎年改善するわけではないし、課題は山積みだ。だが、人類が大いなる進歩を遂げたのは間違いない。これが、「事実に基づく世界の見方」だ。

2019年に話題になったファクトフルネスの主テーマとなるような名文。
世界は良くなっている。
「ファクトフルネス」は、2019年に読んだ本の中から第3位に選定し紹介した本です。
瀧本哲史『ミライの授業』の名言

▶ミライの授業(瀧本哲史)に書かれた名言・名文
例えばいま、みなさんが真っ赤なレンズのメガネをかけているとします。そこから見える世界は、きっとおかしな色になりますよね?そんなメガネ、すぐに外してしまうでしょう。
でも、自分の知らないうちに、それこそ赤ちゃんのことからずっと赤いメガネをかけていたら、どうなるでしょうか?
・・・そう。たぶん自分が赤いレンズを通して世界を眺めていることに気づかないまま、ほんとうの色を知らずに「世界はこんな色なんだ」と思い込んでしまうはずです。ベーコンは、こうした思い込みから抜け出さないと、ほんとうに「知」には、たどり着けないと考えました。
人間は、心の中で、どんな「思い込み」のメガネをかけているかわかりません。
前田裕二『メモの魔力』の名言

▶メモの魔力(前田裕二)に書かれた名言・名文
メモを癖にしてしまえば、言葉にすることから逃げられなくなります。
生活している中で「すごい」や「やばい」といった簡単な形容詞で片付けてしまったり、通り過ぎている感動は、数え切れないほどあると思います。果たして、何がすごくで、やばいのか。
ここを一歩二歩踏み込んで考えるのが、本質的なメモのあり方です。
木崎伸也『アイムブルー』の名言

▶アイムブルー(木崎伸也)に書かれた名言・名文
誰かに踊らされてることに気づかないことだ。それに気づかないから、どうでもいいことに右往左往したり、人のせいにしたりする。
そんなヤツらと一緒に戦場に行ったら、間違いなく命を落とす。
「オススメのサッカーにまつわる本」を紹介した記事があるので、興味のある方は読んでみてください。
吉田修一『続 横道世之介』の名言

▶続 横道世之介(吉田修一)に書かれた名言・名文
わりと鮮明に思い出せるのは、この月が自身の誕生月だからで暇さえあればパチンコ屋に通うようになっていた時期で、ああ、これが厄年というものかと、半ば投げやりになってもいたが、それでもあれから今日までの一年間を全部なかったことにしましょうと言われれば、「いやいや、それでもちょっとはいいこともあったんですよ」と、決して充実していたとは言えない日々ながらも、ちょっとだけキラキラした思い出はいくつも浮かんでくる。そして、きっとそれが一年というものだ。
しかし、栗原の兄貴はその一年という日々を「いらない」と言っているのだ。そんな人間がいることが、世之介はどこか悲しい。それが広島風お好み焼きを焼いてくれたお兄さんかと思えば、なお悲しい。

この小説の素晴らしさが現れた文章。
横道世之介シリーズは、三作目も読みたい。吉田修一さん、書いてくれないかなあ。
この本は、2019年に読んだ本の中で第6位に選定した本です。
また、オススメの小説として紹介した記事もあります。
箕輪厚介『死ぬこと以外かすり傷』の名言

▶死ぬこと以外かすり傷(箕輪厚介)に書かれた名言・名文
東松寛文『サラリーマン2.0』の名言

▶サラリーマン2.0(東松寛文)に書かれた名言・名文
意外と気づいていないだけで、わざわざやっていることは、きっと誰でも持っているはず。それは仕事の中であるかもしれませんし、プライベートの中にあるかもしれません。大事なのは、そのわざわざやっている理由です。
その理由の先に、きっとあなただけの強みが待っています。
やりたいことを見るけるために、やみくもに新しいことを始める必要なんでないのです。
荻田泰永『考える脚 北極冒険家が考える、リスクとカネと歩くこと』の名言

▶考える脚 北極冒険家が考える、リスクとカネと歩くこと(荻田泰永)に書かれた名言・名文
自分がやるべきこと、自分にしかできないこと、やりたいこと。
その3つを人生においてどう重ねていくか。
自分だけの自己満足を徹底的に行うことで得た力を、誰かのために使うことで、意味や価値を生み出せるという自信がある。
坪田信貴『世界に一つだけの勉強法』の名言

▶世界に一つだけの勉強法(坪田信貴)に書かれた名言・名文
本当にそうなのでしょうか?
物事は「短時間で目的を達成するほどエライ」のが鉄則。なのに、勉強だけが時間をかけるほどエライとされているのです。
それは「手段の目的化」という現象が起こっているからです。

とても納得。できるだけ短い時間で、最大の効果を。
著者の坪田信貴さんは、「ビリギャル」の作者として有名な方です。吉本興業の会長である大﨑洋さんとのラジオがとても面白くて、そこで話していた「感性を磨きなさい」という言葉から感じたことを書いた記事があるので紹介します。
坪田信貴『才能の正体』の名言

▶才能の正体(坪田信貴)に書かれた名言・名文
親御さんはわが子に対して「やる気を持ってほしい」と言いますが、その子は「遊びたい」という強い動機づけがあって、「勉強したい」という動機づけがないだけです。動機のない子なんて、一人もいません。

動機づけはとても大切。全ての行動には動機があるのだから。
2019年の第8位に選定した本です。
国分拓『ノモレ』の名言

▶ノモレ( 国分拓)に書かれた名言・名文

これはフィクションでは考えられないような、その感覚をもったことがある人にしか書くことができない名文。
2019年に読んだ本の第一位を獲得した国分拓さんのノモレです。
また、オススメの旅本でも紹介しています。
松岡修造『弱さをさらけだす勇気』の名言

▶弱さをさらけだす勇気(松岡修造)に書かれた名言・名文
しかも、一瞬早すぎず、一瞬遅すぎないときに。
しかし、うちに求める心なくば、眼前にその人ありといえども、縁は生じず。

後半部分が秀逸で、やっぱり受け身だといろんなチャンスを見逃してしまう。
求める心はとても大切。
幡野広志『ぼくたちが選べなかったことを、選びなおすために。』の名言

▶ぼくたちが選べなかったことを、選びなおすために。(幡野広志)に書かれた名言・名文
病気になってからは友人たちも選びなおし、ますます人生が輝いていった。
生きるとは、「ありたい自分を選ぶこと」だ。なにかを選びはじめたとき、その人は自分の人生を歩きはじめる。誰かに奪われかけた自分の人生を取り戻す。
ぼくはこれからも自分を選び、自分の人生を選んでいきたい。

主体的に生きられるかどうかで人生の充実度は大きく変わる。
では、どうしたら主体的に生きる人になれたり、そんな人を育てられるのだろうか?
自分で決めていくことの大切さがこの文章には詰まっている。
2019年に読んだ本の第5位に選定した本です。
また、幡野広志さんの本については、「ぼくたちが選べなかったことを、選びなおすために。」や「他人の悩みはひとごと、自分の悩みはおおごと。 なんで僕に聞くんだろう。」で書評記事を書いています。合わせて読んでみてください。
幡野広志『ぼくが子どものころ、ほしかった親になる。』の名言

▶ぼくが子どものころ、ほしかった親になる。(幡野広志)に書かれた名言・名文
なぜ、そんなことになったのか知りたくて尋ねると、とても多かったのが、「親が全部決めていました」という人たちだった。
学校や進路という大きなことから、部活や習いごと、洋服、趣味、あげくには「ファミレスで何を食べるか」という小さなことまで、親が決めているケースがほとんどだった。
わがこに失敗させたくない、間違いがない、ベストの道をいかせてあげたいという親心なのだろうか。
「それじゃなくて、こっちにしなさい」
子どもが選んだものを否定して、自分が良いと思ったものを押し付ける親の姿だ。
それはたかがお菓子だけれど、親の「それじゃなくて、こっちにしなさい」は、やがてファミレスのメニューになり、洋服になり、学校選びになり、部活や習いごとになり、つきあう友だちや彼女、彼氏におよぶ可能性もある。
こうして「やりたいことが見つからない」人ができあがる。

こちらも幡野広志さんの本。
僕自身で考えると、一人娘がかわいくてついつい先回りをして失敗しない方法を見つけてしまうけれど、失敗しないことがいい教育なわけではない。大切なことを実感させられる一冊。
こちらは、2019年の第2位に選定した本です
若林正恭『ナナメの夕暮れ』の名言

▶ナナメの夕暮れ(若林正恭)に書かれた名言・名文
誰と会ったのかと誰と合ったのか。
俺はもうほとんど人生は“合う人に会う”ってことで良いんじゃないかって思った。それは家族だし、友だちだし、先輩だし、後輩だし、仕事仲間だし、ファンだし、相方だし。
そういう合った人にこれからも会えるようにがんばるってことが、結論で良いんじゃないかなって思った。

若林正恭さんのこういう人間くさい文章が好きです。
若林正恭『表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬』の名言

▶表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬(若林正恭)に書かれた名言・名文
でも、例えば人生とか、愛とか、感謝とかって実はアメフトの話のようなものの中に含まれていて、わざわざ言葉にして話すようなことじゃないんだ。

お父さんの病気がわかって、今日はとことん語らおうと思っていたけれど、いざそんな場面に直面すると、普段と全く変わらない話しかできない。だけど、普段と変わらないいつもの言葉の中に、愛とか感謝が実は入っている。
2019年に読んだ本から第4位に選定した本です。
また、オススメの旅本でも紹介しています。
糸井重里『思えば、孤独は美しい』の名言

▶思えば、孤独は美しい。(糸井重里)に書かれた名言・名文
・悪口を言うのはやめられないことだ。
・しかし、悪口を言うのは恥ずかしいことだ。
・いまの時代の悪口は、本人に届くものだ
岸政彦『図書室』の名言

▶『図書室(岸政彦)』に書かれた名言・名文
それなりにいろいろなことがあって、自暴自棄になり、荒れ果てていた学生生活のなかで、奇跡的に訪れた二度と味わえない、自由と平穏の三十分だった。
それが、私にとっての吹田だ。

非日常の体験が特別なわけではなく、日常の中に特別な体験がある。
後から振り返ったときに思い出すのは、そんな日常の中の出来事が多い。
岸政彦さんは、「断片的なものの社会学」がめちゃくちゃ面白く、オススメのエッセイでも紹介しているので、ぜひ読んでみてください。
中村禎『最も伝わる言葉を選び抜くコピーライターの思考法』の名言

▶『最も伝わる言葉を選び抜くコピーライターの思考法(中村禎)』に書かれた名言・名文
せっかくいい言葉を見つけても、それに気づいていなければ、書いていないのと同じことです。
学ぶとは、自分が感動すること。
教えるとは、自分の姿勢を見せること。

「言葉」を「写真」と置き換えても同じように思う。
いい写真を発表する人は、いい写真を撮るだけでなく、いい写真を選び、いい写真をプリントできる人。
本の名言記事で紹介した本はaudibleで聴ける?
僕が2019年に読んだ本から名言を紹介した記事から『メモの魔力』『才能の正体』がaudibleの聴き放題対象本としてありました。
オーディブル(audible)は、Amazonが提供している聴く読書サービスで、入会最初の1ヶ月間は無料体験を実施しています。つまり、1ヶ月間は聴き放題対象作品の本が全て無料で聴けるサービスなので、めちゃくちゃお得です。
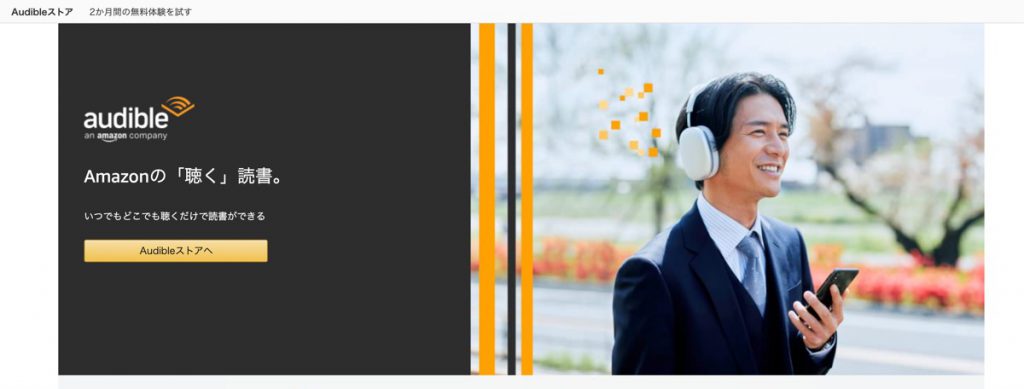
今回紹介した『メモの魔力』『才能の正体』は1ヶ月間は無料で聴けるし、傑作ノンフィクション『サピエンス全史』や、お金の悩みのヒントをもらえる『ジェイソン流お金の増やし方』など、話題の本が全て無料で聴けます。
「聴く読書」をまだ試していない方は、この機会にぜひ登録して試してみてください!
もちろん無料体験期間内に解約すれば、完全無料。解約も簡単です。
この機会に、ぜひ登録して試してみてください!
『audibleオーディブル』の話題が出たので紹介すると、audibleは聴き放題と言ってもたいした本がないんでしょ?と考える方もいらっしゃるかと思いますが、これがビックリするほど読み応えのある本が揃っています。
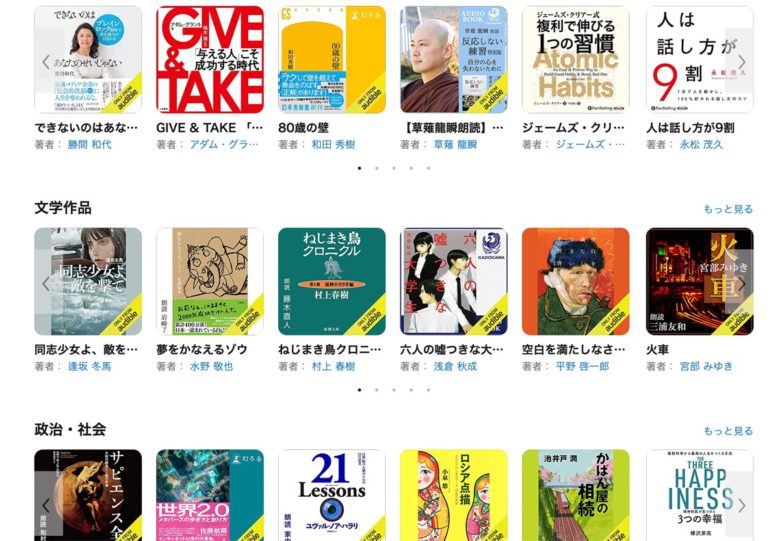
このブログでは、audible(オーディブル)について詳しく書いた記事があるので、興味のある方は読んでみてください!
読書が楽しくなる本の名言を紹介
このブログでは、本に書かれていた名言を紹介する記事がいつくもあります。
毎年読んだ本に書かれていた名言・名文を紹介した記事や、小説家・探検家・写真家の名言を紹介した記事もあります。
『本の名言』を幅広く知りたい方は、各年に読んだ本の名言を紹介した記事がオススメです。
本は普段は関わることのないような特別な思考をもった人たちの頭の中をのぞけることが魅力です。
小説家・伊坂幸太郎さん、探検家・角幡唯介さん、写真家・星野道夫さんといった稀有な存在の名言を紹介した記事もオススメです。
「マンガ」や「旅本・紀行文」といったジャンルの名言・名文もオススメです。
2019年に読んだ本から心に響いた名言 まとめ
2019年に読んだ本の中から20の名言・名文を選んで紹介しました。
僕は本を読んでは、好きな言葉をノートにうつす作業を15年間ずっと続けています。
自分の血となり肉となったノートをたまに見返しては、勇気をもらい、前に進んでいるような気がして、この習慣をずっと続けています。
2019年もたくさんの言葉をノートに綴った。
きっとこのノートが僕を救ってくれるんだろうなと思っています。