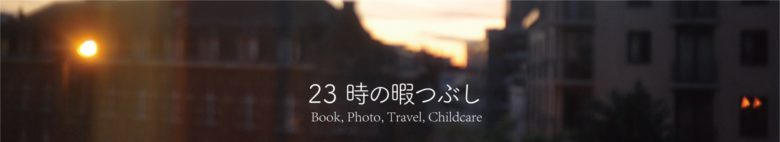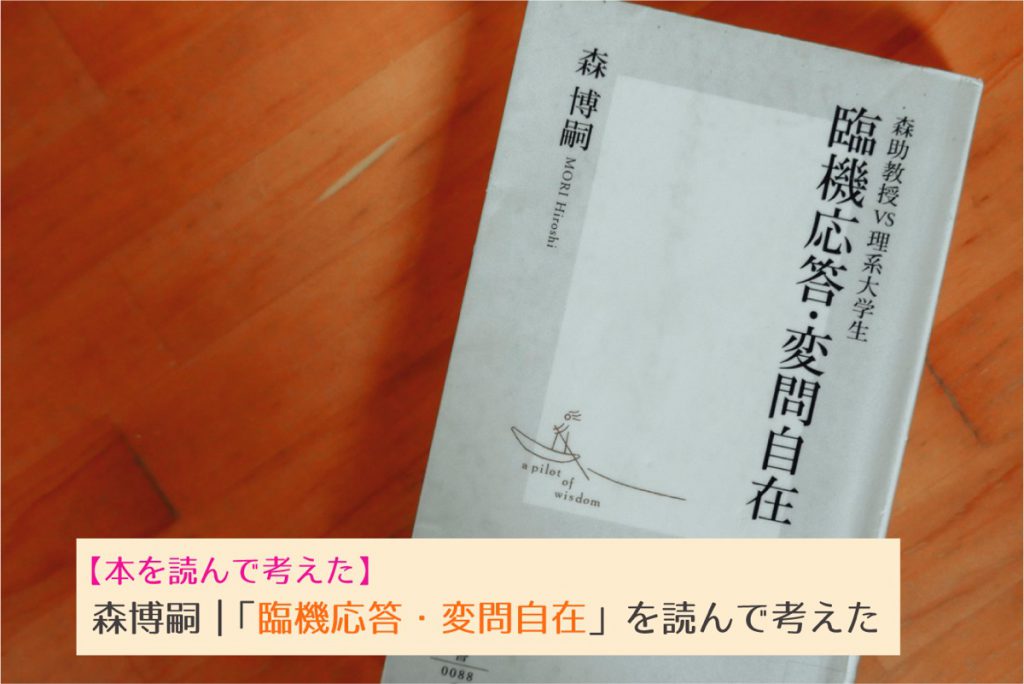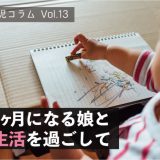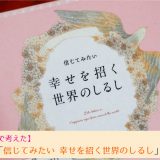この記事では、幻冬舎から出版されている「森博嗣さんの著書『森助教授VS理系大学生 臨機応答・変問自在』の書評記事」です。「すべてがFになる」やスカイ・クロラシリーズで人気の森博嗣さんが「大学生に質問をさせる授業」です。
 どこよりも詳しい読書感想文の総まとめ|読みたい本が見つかる
どこよりも詳しい読書感想文の総まとめ|読みたい本が見つかる目次
森博嗣さん著『森助教授VS理系大学生 臨機応答・変問自在』とは?
森助教授VS理系大学生 臨機応答・変問自在|森博嗣

先日、この本の著者の森博嗣さんの「作家の収支」を読んで考えたことの記事を書いた。
内容はそれこそ作家の収支が書かれた本で、小説雑誌の原稿料、単行本の印税、対談本の出版や入試問題に使われた場合、解説や推薦文、講演料など、その作家活動での収支を事実として細かく報告してくれている一冊だ。
誰の参考になるかわからないけれど包み隠さず分析的に書かれていて、読み物として面白いので興味があれば是非読んでみてほしい。
その森博嗣さんが名古屋大学の学生との授業で行った質問応答をまとめた本が、今回紹介する「森助教授VS理系大学生 臨機応答・変問自在」だ。
パーソナルなものや建築に関わることなど、学生の質問に淡々と答える回答から、森先生の頭の中の一片を覗き見することができる。
「森助教授VS理系大学生 臨機応答・変問自在」に書かれた森博嗣さんの名言・名文
僕は本を読んだら気になった文章をノートに書き記す習慣を、もう15年近く続けている。
インプットの吸収率が圧倒的に上がるし、なにより目に見える形で記録されていくことが自分の自信になる。
本書から気になった文章を紹介する。
人は、どう答えるかではなく、何を問うかで評価される。
たとえば、就職の面接で、「何か質問はありませんか?」と面接官に尋ねられたとき、的確な質問ができるかどうか、そこで評価される。準備された回答を暗記して、それを正しく再生する能力ばかりが期待されているのではない。会話の中で、議論の中で、何が不足しているのかを常に意識し、それを的確に把握して質問をする能力が重要であり、つまり問題を考える行為に集約される。
したがって、本当に人の能力を観たいときは、何を答えるかではなく、何を問うか、を観るべきであって、現にそうした評価がなされている場合が多い。
まずは意識してものを問う姿勢が重要なファクタとなるだろう。
ただし、それが成り立つ唯一の条件がある。アドバイスを受ける側の人間が、積極的な姿勢でアドバイスを活かそうとしている場合だ。受け手にその姿勢があるときに限り、おそらくほとんどのアドバイスが有効となる。人生相談というものが見かけ上成立している背景には、このようなメカニズムがあるものと推察する。
人生相談が見かけ上成立している背景のメカニズムとか推察したことがなかった(笑)
おもしろいですね。
なんにせよ主体的に行動することで見える世界が変わると思っていて、それと通じることなのだろうなと思う。
森博嗣さん著「森助教授VS理系大学生 臨機応答・変問自在」を読んだ感想・まとめ
この本のそもそもの意図が実は一番おもしろくて、ちょっと解説する。
森先生は、この講義の評価基準を「質問力」とした。
授業終わりに学生が質問用紙で質問を投げかけ、その質問力で学生を評価するということだ。
その意図として、質問する力は理解度と関係すると本書で書かれている。
確かに、それはあるかもしれない。というか、おもしろい。
「質問が効果的な人」は話していて楽しいし、話していて楽しいのはきっとそのことについて考えて自分なりの意見や疑問をもつからだろう。
そういった姿勢や理解度を評価に設ける発想は、おもしろかった。
この記事のように『教育』をテーマとした本の読書感想文としては落合陽一さんの子育て論が書かれた本『『0才から100才まで学び続けなくてはならない時代を生きる学ぶ人と育てる人のための教科書』や、『鈴木賢志|スウェーデンの小学校社会科の教科書を読む』などがあります。
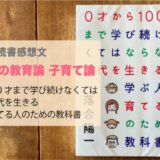 落合陽一さんの教育論・子育て論を解説した本の読書感想文
落合陽一さんの教育論・子育て論を解説した本の読書感想文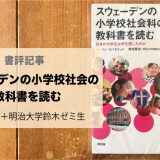 おすすめ教育本『スウェーデンの小学校社会科の教科書を読む』本の紹介と感想文
おすすめ教育本『スウェーデンの小学校社会科の教科書を読む』本の紹介と感想文他にも超話題となった『ブレイディみかこ|ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』も、広義で教育に関わる本と言っていいような一冊で、全ての人に読んでもらいたい一冊です。
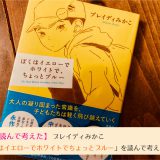 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー|あらすじ感想
ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー|あらすじ感想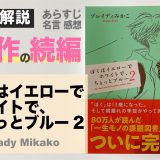 『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー2|ブレイディみかこ 』あらすじと感想
『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー2|ブレイディみかこ 』あらすじと感想これまでの読書感想文一覧をリンクとして貼っておきますので、興味のある本があればぜひ読んでみてください!
 どこよりも詳しい読書感想文の総まとめ|読みたい本が見つかる
どこよりも詳しい読書感想文の総まとめ|読みたい本が見つかる1)角幡唯介|エベレストには登らない
2)菅俊一・高橋秀明|行動経済学まんが ヘンテコノミクス
3)中田敦彦|中田式ウルトラ・メンタル教本
4)戸田和幸|解説者の流儀
5)石川直樹|この星の光の地図を写す
6)岸見一郎|哲学人生問答
7)渡邊雄太|「好き」を力にする
8)高橋源一郎|ぼくらの文章教室
9)石川直樹|まれびと
10)堀江貴文|英語の多動力
11)森博嗣|作家の収支
12)鈴木敏夫|南の国のカンヤダ
13)森博嗣|森助教授VS理系大学生 臨機応答・変問自在←今回の記事
14)米沢敬|信じてみたい 幸せを招く世界のしるし
15)馳星周|馳星周の喰人魂
16)藤代冥砂|愛をこめて
17)佐藤優|人生のサバイバル力
18)せきしろ|1990年、何もないと思っていた私にハガキがあった
19)服部文祥|息子と狩猟に
20)ブレイディみかこ|ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー
21)河野啓|デス・ゾーン 栗城史多のエベレスト劇場
22)幡野広志|他人の悩みはひとごと、自分の悩みはおおごと。
23)内山崇|宇宙飛行士選抜試験 ファイナリストの消えない記憶
24)近藤雄生|まだ見ぬあの地へ 旅すること、書くこと、生きること
25)岸田奈美|家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった
26)玉樹真一郎|「ついやってしまう」体験のつくりかた
27)村本大輔|おれは無関心なあなたを傷つけたい
28)小松由佳|人間の土地へ
29)服部文祥|サバイバル家族
30)石川直樹|地上に星座をつくる
31)加藤亜由子|お一人さま逃亡温泉
32)沢木耕太郎|深夜特急
33)ブレイディみかこぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー2
34)沢木耕太郎|深夜特急第1巻・第2巻
35)沢木耕太郎|深夜特急第3巻・第4巻
36)いとうせいこう|国境なき医師団を見に行く
37)ちきりん|「自分メディア」はこう作る!
38)村上春樹|村上T 僕の愛したTシャツたち
39)鈴木賢志|スウェーデンの小学校社会科の教科書を読む
40)沢木耕太郎|深夜特急第5巻・第6巻
41)落合陽一|0才から100才まで学び続けなくてはならない時代を生きる学ぶ人と育てる人のための教科書|
42)早坂大輔|ぼくにはこれしかなかった。BOOKBERD店主の開業物語|
43)小永吉陽子|女子バスケットボール東京2020への旅
44)辻山良雄・nakaban|ことばの生まれる景色
45)岡田悠|0メートルの旅
46)トム・ホーバス|チャレンジング・トム
47)長谷川晶一|詰むや、詰まざるや 森・西武VS野村・ヤクルトの2年間
48)田中孝幸|13歳からの地政学
49))国分拓|ガリンペイロ
50))サトシン・西村敏雄|わたしはあかねこ
51))林木林・庄野ナホコ|二番目の悪者